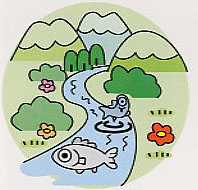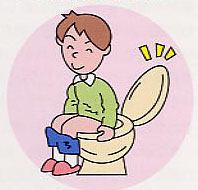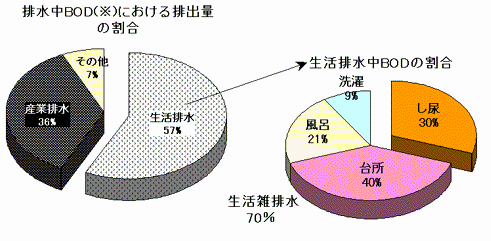下水道の役割と効果
下水道の役割と効果
まちに下水道が普及することにより、次のような効果が期待できます。
公共用水域の保全 |
生活環境の向上 |
トイレの水洗化 |
|
|
|
|
|
汚水を集めてきれいにするので、紀の川などの水質が守られます。 |
排水が川や溝を流れなくなるので、ハエや臭気の発生が少なくなり、伝染病の流行を抑えることにも役立ちます。 |
水洗トイレが、個別の浄化槽が無くても使えるようになります。 |
(古くから下水道整備が行われた都市では、汚水、雨水とも下水管に流すので、下水道は洪水を防ぐ役割もあります)
また、下水道施設で処理された水を、トイレ用水や散水用水など(いわゆる中水道)に利用したり、処理施設から発生する汚泥を建設資材や肥料として製品化するなど、有効利用されている例があります。
 川の汚れの原因
川の汚れの原因
ではなぜ、下水道が使えるようになると、川や海がきれいになるのでしょうか。下のグラフをご覧下さい。
|
|
|
出典:和歌山県「生活排水を考える」パンフレットより |
このグラフが示すとおり、家庭から出る汚水(生活排水)のうち、生活する上で排出される台所、お風呂などからの水(生活雑排水)を処理すれば、環境に与える悪影響を大きく減らすことが出来ます。また、下水道のイメージはどうしてもトイレと結びついてしまいますが、下水の成分でし尿の占める割合は約3割で、意外と少ないことがわかります。
下水道や集落排水事業、浄化槽などの汚水処理施設は、雨水以外の家庭から排出される水すべてを集めてきれいにします。また下水道は生活排水の他に、工場からの排水も処理します。他の地域でも、下水道が普及し河川が浄化され、一時姿を消していたホタルやアユなどの生物が戻ってきた等、整備の効果が現れています。
なお、し尿のみを処理する、みなし浄化槽(単独処理浄化槽)は、生活雑排水を未処理のまま排出してしまうので、下水道への接続や浄化槽への改造などの対策が急がれます。
(平成13年の法律改正により、以前の「合併処理浄化槽」は「浄化槽」となり、「単独処理浄化槽」は「みなし浄化槽」と呼ばれるようになりました。現在ではみなし浄化槽の新設は出来ません。)
 どれぐらいきれいになるのでしょうか
どれぐらいきれいになるのでしょうか
 流入水は茶色くにごり、下水の臭いがしますが、放流水は魚が住めるぐらいまできれいになります。放流水の一部を伊都浄化センター内せせらぎ水路に導き、コイ、金魚、ハヤなどを放しています。
流入水は茶色くにごり、下水の臭いがしますが、放流水は魚が住めるぐらいまできれいになります。放流水の一部を伊都浄化センター内せせらぎ水路に導き、コイ、金魚、ハヤなどを放しています。
下水道が普及すれば、いままで未処理で流されていた水も浄化されるので、紀の川の水質が更に良くなることが期待されます。
|
|
|
↑せせらぎ水路の様子 |